

今年も激戦だった。特に800万未満と1500万未満は、部門賞候補が複数あり、甲乙つけがたい状態で本当に苦労した。来年からは、部門賞に、部門グランプリに加えて、部門の準グランプリを作ってほしい(笑)
さてリノベーションが浸透し始め15年以上の年日が過ぎた。間もなく次の10年の「住生活基本計画」が策定されようとしている。計画素案では、新築には高みを目指した性能を求める、住宅地開発は未来を見通して必要なものに厳に制限すると書かれ、明確に既存住宅、既成住宅地を活かすことを謡っている。日本は新築主軸の住宅政策であったが、人口減とともに建築費の高騰が相まって、急激に既存シフトが起きている。首都圏の新築分譲マンションは、年間8万戸×13年供給されていたが、今は2万戸台に激減。検討サイドも新築買えない中古ではなく、当初から中古・既存を主軸に探すように。その中古マンションすらも中心部は高騰化し、代替としての中古一戸建てのニーズが増大している。
さて今年の傾向だが、特にマンションにおいて「デザイン回帰」」の印象があった。総合グランプリの「人間は、つくることをやめない」、1500万円未満の部門賞の「わたしのための、パブリックスペース」1500万円以上部門、家族の「退屈」をリノベした「心、躍るいえ。 〜退屈を、リノベーションする〜」。請負リノベーションはもちろん、再販型でもコンセプチュアルなものが出てきた。また4号特例の縮小に伴う対応提案「ガリバーを解き放て!」も今風だなあと感じた。
もう一つは対象ターゲットの拡大。単身世帯が40%超に達する中で、同世帯向けのリノベーション、子供の数よりペット飼育数のほうが多い日本でのペット重視の案件も目立った。今後は、団塊世代の相続財産を受けとる50~60代の住み替え活性化に期待している。60歳前後の方々が、思わず住み替えたいとテンション上げる「心躍るリノベーション」を、間取り、品質、コミュティ含めたデザインで提案してほしい。、またマンション再販だけでなく、戸建て再販でも期待したい。

2025年の入賞作品全体を通して感じたのは以下の6つ。
1.孫(高齢化の影響で、孫が祖父母の家をリノベーションすることが今後はもっと多くなりそう)
2.猫(国内の飼育頭数が犬より多くなっていることが影響しているのか、ペットをテーマにした切り口ではない作品にも多く登場。ビジュアル的にも有利)
3.再販(多様なニーズにマッチする優れた事例が増えている。個人宅よりも濃く世相を反映)
4.性能向上(補助金等による国の後押しもあり、ユーザーの意識も高くなりつつある。広いお宅は部分断熱が現実的)
5.引き算(ネガティブなコストダウンではなく、要不要をしっかりと見極めた上で自分にとって大切なものやことを優先)
6.サーキュラーエコノミー(循環そのものを目的とするのではなく、それをフックとしたより社会的なインパクトのある取り組みが増えている)
写真のクオリティは数年前からとても高くなっていると感じていましたが、今年はテキストに関してもそれを感じました。AIなどもうまく活用されているのかなと思いますが、ポイントがわかりやすくまとめられていて、設計の意図や住み手の暮らしぶりなどもイメージしやすかったです。
グランプリの人間は、つくることをやめないは、既存建物の希少価値に加えて、リノベーションのプロセスそのものを楽しんでいる点、華やかだけれど親しみやすいビジュアル、要点がきちんと整理されたテキスト、シンプルで力強いタイトル、すべてが優れていて、グランプリにふさわしい作品だと感じました。
賃貸ビジネスにおけるサーキュラーエコノミーへの取り組みは、サーキュラーエコノミーをフックとして、これからのリノベーションや賃貸住宅のあり方に一石を投じる作品。デッドストックや端材を活用することを目的化せず、既存建物の良さを生かした内装、景観との調和、賃貸ビジネスとして成立する、という点もきちんとクリアしているのが良いと思いました。
となりあう囲い は、まずマンションの中に弓道の練習場(と防音室)というインパクトと、工事費が960万円、という点で審査会で大いに話題となりました。また、個人的には施主さんの「空間が細かく分かれている方が落ち着く」という感覚に強く共感。大人数で、広い場所で共に過ごすことがしんどくなってきたお年頃のせいなのかもしれません。それぞれの寝室と趣味のスペースのほかに共有スペースもしっかり確保されていますし、生活動線もとてもよく考えられたプラン。住み手のご夫婦はまだお若いようですが、会社をリタイアした後やお子さんが巣立った後はこんな風に暮らしたい、という方も多いのではないでしょうか。

「ガリバーを解き放て!」
4号特例の見直しに伴って、2階建て木造戸建て住宅でも「大規模の修繕・模様替え」に該当する場合は建築確認が必要になった。大規模に当たるかは「主要構造部の過半」を改修するかどうかで決まる。大幅な規制強化であり、リノベ事業者にとっては悩ましい問題だろう。今後は、複雑な建築基準法令を読みこなし、実務で使いこなす能力が、これまで以上に求められるようになる。国土交通省のガイドラインなどを読み解き、既存の外壁を新たな外装材で覆うカバー工法などを使って、大手住宅会社が建てた築40年近い住宅を爽やかに生まれ変わらせた本作は、その先駆例といえるかもしれない。断熱性能も十分に確保し、新たな住人の生活を支えている。
「工種を絞って、人気エリアに総額2,000万円でマイホーム」
間取りの変更は最小限に、設備のグレードを落とし、欲しかった家具はあきらめて――。人手不足と建設費高騰の時代、思い描く住まいをかたちにするのは、結構、大変だ。見方を変えれば、リノベーション事業者の腕の見せ所でもある。住まい手が好みそうな建材を手堅く押えてデザイン性を高めつつ、塗装やタイルは使わずに左官や大工工事で済ませる。工種を減らして工事費を削減したこの再販物件には、プロならではの視点がキラリと光る。大量の仕事を効率的にこなすため、水平分業が進んできた建設業。今はその転換点ではないだろうか。既存の生産システムと、住まい手のニーズの折り合いを付けたこの事例は、大いに参考になるはずだ。
「「棲み分け断熱」という、暮らし方」
全ての新築住宅が省エネ基準への適合を求められるようになり、断熱性能は今や耐震性能などと並ぶ家づくりの重要項目となっている。しかし、築年数が古い住宅を、現代の基準に適合させるのは容易ではない。本作のタイトルにもなっている「棲み分け断熱」は、快適な暮らしを、限られた予算内で手に入れるための現実解だ。もっとも、断熱改修をLDKなどに絞るゾーン断熱は、ともすれば安っぽい印象に陥りがち。本作は、アップサイクルした木製建具をうまく使いながら、昭和の住まいを品良くアップデートしている。思い切って無断熱とした和室などを、シェルター化したLDKと外界の「緩衝帯」のように位置づけているところにもセンスを感じる。

2016年9月にスタートしたTOKOSIEは、来年で丸10年になります。この10年間「どうしてリノベーションをしようと思ったんですか?」という問いを、取材の度に投げかけてきました。
設備が古くなってきたから新しくしたい。趣味を存分に楽しめる空間がほしい。集中できる仕事部屋がほしい。子供が大きくなったから個室がほしい。子供が巣立ち部屋数を減らしたい。無数の答えがありました。そして、その答えは時代とともに変化し、絶えず新しい答えが生まれていきます。
私は今年でリノベーションオブザイヤーに参加させていただき3年目になります。年の瀬に、皆様と一緒に1年を振り返り、答え合わせをする時間となっています。
今回の選考会で特に印象的だったのは、中古戸建の一軒家をリノベして1人で暮らす女性の事例が2つも入賞していたこと。事例「地方空き家、これからのかたち」「猫と私の『Purrfect Meow-zy』」
家族団欒の場として建てられた一軒家が、時を経て、おひとり様バンザイ!な自立した女性の住まいへと成長を遂げています。
住まいづくりは大きな買い物だからこそ、自分にとってのベストな選択を考え抜き、自分ととことん向き合う時間。お施主さん1人1人と膝を突き合わせ、一緒に答えを見つけていく皆様と、この場をご一緒させていただけることを光栄に思います。

昨年のリノベーション・オブ・ザ・イヤーの講評では、既存の価値を「壊さず、活かす」視点が多く見られた点に触れた。今年は、その考え方がより“共有しやすい形”として立ち上がった一年だった。個別に積み重ねられてきた工夫が、他の事業者が見ても自分のプロジェクトに置き換えやすい具体性を帯びており、単独の成功例にとどまらず横展開できる実践として評価できた点が、今年の受賞作に共通していた特徴だと言える。
まずグランプリを受賞した「人間は、つくることをやめない」(合同会社つみき設計施工社)から触れたい。1970年代の量産住宅を対象に、既存の枠組みを壊すことなく多様性に対応できることを示した。規格化ゆえに個性を出しにくいとされてきた住まいに対し、既存を前提としながら変化を生み出す具体例となった点が評価の中心にある。同様の制約条件に向き合う設計者にとっても、自身の現場に応用する余地を感じられる点は、本作の社会的インパクトの一つだ。
続いて、800万円未満部門最優秀賞を受賞した「市営住宅のあり方を、団地の経験値で解く」(株式会社フロッグハウス)は、築古の市営住宅を500万円で改修し、断熱・防音・換気といった住環境の要点に的確に投資した判断が際立つ。使える部分を残し、改善すべき点に絞って更新する姿勢は、団地リノベの経験値に裏付けられたものであり、限られた予算でも再現しやすい実践として評価できる。自治体が抱える築古ストックの課題に対し、住まいとしての質を底上げし、若い世代の定着にもつながりうる点に価値がある。
さらに、無差別級部門最優秀賞の「未踏の集落リノベーション、月見台住宅*」(株式会社エンジョイワークス)は、全戸空き家となっていた公営平屋群を解体せず、58戸を集合体として再編した点に意義がある。単体の更新ではなく、既存ストック全体を“集落”として捉え直し、公営住宅を地域の資源へ転換した。不動産投資型クラウドファンディングによる事業構造や、投資家がDIYに関わる仕組みは、維持管理の担い手を広げる新たな試みとして注目される。
今年の受賞作から浮かび上がったのは、既存を前提にしながら住まいを更新するための工夫が、量産住宅から市営住宅、“集落”へと多様なスケールで実践されていた点である。壊すのではなく活かすという姿勢は、限られた条件の中でも暮らしを豊かにする可能性を広げ、多様な暮らし手が自分に合った住まいを築くための柔軟な選択肢を生み出していく。こうした取り組みの積み重ねが、リノベーションをより大きな価値へと育てていく土台になると感じている。

リノベーションオブザイヤー2025にはいくつかの傾向がみられたと思う。
ひとつは住宅の基本機能のアップデート。みかけだけでない断熱・空調・耐震性能など住宅機能のアップデートが改めて本質としてリノベーションの中心に据えた事例が多かった。特に800万円以下の部門最優秀賞「市営住宅のあり方を、団地の経験値で解く」は、賃貸市営住宅の断熱・換気機能の改善と最小限の住宅設備のリノベーション。500万円でできるリノベーションの優先を“暮らす環境の改善”という本質にたちかえった事例といえる。
もうひとつは空間の考え方。過去の住まいの設計を残し、センス良く再構築した事例も見られた。元の造作家具を活かした「時をかける部屋 リノベ再販だからこそ愛着が持てる住まいへ」や、内井昭蔵のモダニズム建築の傑作 桜台コートビレジを昇華させた「健康な建築」がそれにあたる。Beforeの住まいの考えをリスペクトし、現代的に再編した好事例だ。
もうひとつは“より自由”なリノベーション。仕切られた壁を取り払い“空間に自由度を戻す”事例は今までもあった。しかし、総合グランプリの「人間は、つくることをやめない」は、がちがちの量産された規格型鉄骨ユニット住宅ですら、施主の“暮らし方への渇望”によって変化するということを見せつける。総合グランプリが示したのは「住まいの自由を自分たちと、自分たちの手で」というリノベーションの民主化。人間が暮らす、人間らしい、自分たちのための、説得力をもつリノベーションだ。
リノベーションの本質と深化、民主化がみられたリノベーションオブザイヤー2025だった。
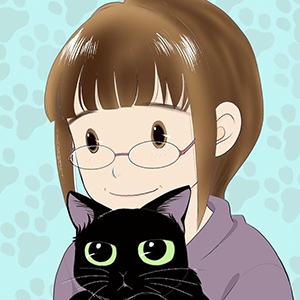
二年ぶりにゲスト審査員として参加させていただきました。
今回も甲乙つけがたい入賞作が並び、その中から各賞を絞っていくのは大変難しかったです。
時代の流れでしょうか。
今回は、単身者、夫婦二人のための施工で目を見張る作品が多かったなという印象を持ちました。
自分だけのため、自分とペットだけのため、夫婦二人のためだけの家は、より個人の生き方、考え方を汲み取り反映させるヒヤリング力とアイディアと柔軟性が必要になることと思います。
入賞作はどれもその力が大きいものばかりでした。
家族が出来たから家を持つ、だけではなくひとりでも、ひとり+ペットでも、ふたりでも家を持ちたいと思わせてくれるリノベーション作品が増えたことを心から嬉しく思います。
気がつけば21世紀が4分の1過ぎていた。
日本のリノベーションシーンは、2000年前後、バブル崩壊による疲弊から回復できぬままの大都会の片隅で、誰も見向きもしないような小さくて古い建物から始まった。当時は一般的にはリフォームという言葉が広く浸透しており、業界人ですら「リノベーションって何??」というほどマイナーな、あるいはサブカルチャー的なムーブメントであった。だが、そこには社会や市場のメインストリームに対するある種の反骨心があり、生まれたばかりのリノベーションはストリートカルチャー的なオルタナティブだった。それから25年間、リノベーションが日本の社会にどれほど広がったかを再確認するのに、多くの言葉を必要としないだろう。
しかし重要なのは、単に広がったという量的な話ではなく、その中身が劇的に多様化したという質的な変化である。リノベーションの多様化とは、すなわち私たちの住まい方の多様化であり、さらに言えば、私たち日本人の生き方そのものの多様化の鏡でもある。2025年のリノベーション・オブ・ザ・イヤーでは、そのことを象徴するような事例が多かったように思う。
たとえば、独身女性が木造戸建てをリノベーションして暮らすという、従来のシングルライフの常識を軽やかに更新する作品。あるいは、住宅団地の再生にあたってクラウドファンディングという新しい資金調達方法を駆使した作品も、審査員に強いインパクトを与えた。また、従来リノベーションが苦手とするハウスメーカーのプレファブ住宅への挑戦もあり、ここ数年質の向上がめざましい買取再販物件もさらなる高みを目指した進化を見せ、昨年のグランプリ作品が提示した、環境性能の概念を拡張させた「サーキュラー」の理念を受け継いだ実践も見られた。こうした作品群にみられるリノベーションの既成概念を自ら書き換えるかのような取り組みは、「リノベーションのリノベーション」と呼ぶことが出来るかもしれない。
さて、エントリー総数206作品の中から2025年のリノベーション・オブ・ザ・イヤーの総合グランプリに輝いたのは「人間は、つくることをやめない」(合同会社つみき設計施工社)である。つみき設計施工社はオブ・ザ・イヤー初エントリーで総合グランプリ獲得という快挙ではあるが、同社は自社を「参加型リノベーション専門工務店」と名乗り、2010年の創業から「ともにつくる」を理念とするDIYリノベーションの仕事を続けてきた。だが、この作品は、単に楽しいDIYリノベーションという範疇には収まらない、日本の近代住宅史に照らしても非常に示唆に富むリノベーションである。
1971年に登場したセキスイハイムM1は、日本の工業化住宅を象徴する鉄骨ユニット工法の先駆であり、住宅需要が急増した時代に対応するため、安定品質と短工期・低コストを可能にした画期的な住宅であった。工場で生産されたユニットをトラックで輸送し、現場で組み立てるだけで熟練した職人を必要としないM1は、住宅から人間の関与を切り離すシステムのようにもみえる。しかし本来M1は、開発した建築家大野勝彦がルームユニットを「無目的な箱」と呼んだように、住まい手の創造性と生活実践によって自由に意味が付与される余白のある器として構想された。それは、ル・コルビジェの「ドミノ・システム」の思想を受け継ぎ、標準化・工業化による大量供給と内部空間の完全な自由の両立を目指すものだった。ところがプレファブ住宅は、その後の普及の過程で商品として洗練を追求し、型式適合認定制度と相まって、住まい手が手を入れにくい完成品としての住宅となっていく。つまり住宅産業の成長の過程で、工業化住宅の根底にあった純粋な理念は置き去りにされたのである。
本作は、その断絶を乗り越える象徴的な試みだと評価できる。専門家が基本的性能を整えた上で、家族と100人以上の仲間が数か月にわたってDIYで仕上げていくプロセスは、まさに箱に新たな意味と感情を与える創造的行為である。実に楽しそうな画像は、まるで「家が笑っている」ようではないか。セキスイハイムM1の思想を再び住まい手の側へ取り戻したこの作品が、工業化住宅に本来あった自由を現代に呼び戻しているからだ。
思えばオブ・ザ・イヤーの初期、2013年〜2016年ごろは、DIYはブームとも呼べるような盛り上がりを見せていた。しかし、その後なぜかリノベーションシーンの表舞台におけるDIYの存在感は薄れていた。ところがここに来て、建築費の高騰や職人不足などでリノベーション工事の実施に現実的な制約が大きくなっている。また建売住宅や買取再販物件のシェア拡大によって住宅がファストな商品化する潮流も強い。このような住宅市場の現状を鑑みれば、もう一度DIYが見直されるべき時期が来ていると提案したい。この作品のグランプリ受賞がDIY復権のきっかけになることを願う。
1500万円以上部門最優秀作品の「ガリバーを解き放て!」(リノクラフト株式会社)も、ハウスメーカーのプレファブ住宅のリノベーションである。プレファブ住宅は、型式適合認定住宅であり、メーカーから設計情報も開示されないため、リノベーションでは最も手を出しにくいストックの代表例である。さらに2025年の改正建築基準法による4号特例の縮小で業界全体が戸建てリノベに及び腰になるなか、本作が示したのは、制度を精緻に読み解く高度な実務能力と難題に挑戦する勇気だ。
確認機関と丁寧に協議しつつ、どこまでの改修が「大規模な改修には該当しない」と見なされ得るのか、そのラインを慎重に見極め、既存構造の強度を活かしたうえで、省エネ性能をZEH適合レベルまで引き上げた。厳しい制度環境の中でも、冷静な技術判断と設計力によってプレファブ住宅のストックはここまで更新できる。その実例を示すことで、業界全体に勇気を与えるメッセージを発した秀作である。
1500万円未満部門最優秀作品は、買取再販マンション「わたしのための、パブリックスペース」(株式会社コスモスイニシア)が獲得した。
近年のリノベーション・オブ・ザ・イヤーにおける買取再販物件の活躍には目を見張るものがある。2015年には6作品しかなかった買取再販物件の入賞(ノミネート)が、2025年には12作品と倍増していることはそのあらわれだろう。コスモスイニシアは提案性の高いコンセプトと優れたデザインの再販物件で2023年、2024年と連続で特別賞を受賞するなど、近年の再販リノベーションの品質向上を牽引してきた事業者の代表選手である。
ついに部門最優秀賞の栄冠を掴んだ本作は、群を抜くコンセプチュアルな提案力と空間デザインの洗練度が評価のポイントである。住まい手が未定の商品であるという宿命を背負った再販マンションながら、「どのような人に、どのように暮らしてほしいのか」を考え抜いた意志が明確である。この強い意志は、冒頭で述べた日本人の住まい方の多様化に対する信頼を土台にしたものであろう。建築価格高騰のおり、53㎡で1480万円というコストは、いまや潤沢な予算というわけではない。その制約の中でも動線や間取りの大胆さ、素材の選定、ディテールへのこだわりなどの総体が、住まい手にとって豊かで自由な暮らしの提案となっている。まさに会心の一撃ともいえる優秀作である。なお、本作は事業者が選ぶプレイヤーズ・チョイスとのダブル受賞で、その汎用性についても高く評価された。
ところで、「買取再販モデルではリノベーション・オブ・ザ・イヤーが取れない」との認識・イメージが事業者の間に根強いのだが、それが誤りであることは、過去のオブ・ザ・イヤーで部門最優秀作品またはグランプリを受賞した買取再販物件を一覧にしてみれば明らかである。特別賞まで対象を広げれば、このリストはさらに長いものになる。このように買取再販モデルのリノベーションは、初期の頃からリノベーション・オブ・ザ・イヤーの一角を占め続けている重要なジャンルであり、請負モデルに比べても遥かに実験的な作品で住まいの未来を提案し続けてきた歴史がある。
こうして一覧を眺めると、買取再販モデルが本来備えている潜在力をあらためて再認識させられる。それは、買取再販物件は事業者の意志によって、これからの住まいの「標準」を先取りして提示できる“パイロットモデル”としても構想可能だということだ。そこには、あるべき住まいの近未来を模索しそれを量産可能なかたちに落とし込むという、請負モデルとは違うもう一つの創造性がある。
確かにこれら受賞作品は、買取再販モデルとしては実験的な特殊解かもしれない。しかし、性能向上にせよまちづくりにせよ、リノベーション・オブ・ザ・イヤーがその年ごとに最もエポックメイキングな特殊解に光を当てることで、業界全体のスタンダードを一歩ずつ押し上げてきたことも正当に評価すべき事実である。現実の市場で大きなシェアを占める買取再販事業における新しい提案や挑戦は、ストック型社会における重要な住宅イノベーションの契機であり、リノベーション文化を次の段階へ導く推進力であることを理解されたい。
800万円未満部門は、近年の建築費の高騰でコストコントロールの工夫がより求められるカテゴリーである。2025年の最優秀賞は「市営住宅のあり方を、団地の経験値で解く」(株式会社フロッグハウス)が獲得した。フロッグハウスは2023年に部門最優秀賞とプレイヤーズチョイスアワードをダブル受賞した「これからの団地リノベのあり方を問う。」に続いての受賞で、団地のリノベーションにおける同社の豊富な知見がいかんなく発揮された作品だ。
本作は、市営住宅という住宅困窮者のためのストック(67.6㎡)を、わずか500万円という厳しい予算条件のもとで、思い切って断熱性能の着実なアップデートに注力した点に大きな価値がある。確かに改修後のUA値0.94 w/㎡kは、現行の新築住宅に求められる最低基準(0.87以下)を満たすものではない。しかし、3面採光ゆえに断熱性能に大きな弱点を抱える市営住宅で、UA値を1.14から0.94へと約17%改善した効果は決して小さくない。ざっくりとした概算になるが、外皮の熱損失が17%減ることで冬季の最低室温は1〜2℃高く保たれ、壁や窓際の表面温度も1〜1.5℃向上する。これにより冷輻射が軽減され、体感温度は実質的に2℃前後改善し、結露やカビのリスクも大幅に低減するはずだ。これは間違いなく生活者のQOL(暮らしの質)を大きく改善する。その上、暖房負荷もおおむね10〜15%低減できるだろう。夏の暑さにもまた然りだ。
性能面だけではなく、リビングに採用された兵庫県産杉の無垢床材は、足触りの柔らかさや温かみ、木目の豊かな表情を通じて、空間に優しい親密さをもたらす。また、壁や建具の色をネイビーに統一したことで、古い市営住宅とは思えない現代的な雰囲気を作り出し、数値だけでは測りきれない暮らしの質を確かに底上げしている。公営住宅に暮らす人の快適さと尊厳をともに高めた本作は、リノベーションの社会的意義を力強く示すものである。
無差別級の最優秀賞に輝いた「未踏の集落リノベーション、月見台住宅」は、長くリノベーションを見て来た審査員たちも度肝を抜かれるほどのインパクトのある作品だった。最終審査会では、総合グランプリの座をめぐって「人間は、つくることをやめない」(合同会社つみき設計施工社)と激しく競い合った。
本作が示した価値は、何よりもまず、絶望的とも言える複合的な予条件を、これまでにないアプローチによって一気に転換した点にある。首都圏でも最も深刻な空き家問題を抱える地域で、築65年以上の荒廃した平屋長屋。それが第一種低層住居専用地域にあり、用途変更も困難。さらに58戸という大きすぎるスケール。通常の発想ではさすがのリノベーションでも打ち手が見つからない、いわば「再生不能」に分類されがちなストックである。
そこに本作は、「なりわい住宅」という第一種住居専用地域でも成立しうる職住一体の住まいとして再生するアイデアで大きな突破口を開いた。そして、計画地全体を秘境の集落として再定義する新たな文脈によって、「山の上の孤島」とも呼ばれる不利な立地に、“ここだからこそ”の価値が立ち上がる。
また、クラウドファンディング=「共感ファンド」による資金調達は、事業のリスクを分散させつつ自発性と意思ある参加者を引き寄せ、再生の主体を広く社会へと開いてみせた。さらに、住まい手だけでなく投資家自身のDIYを積極的に取り込み、58戸の更新を単なる工事ではなく関係性の再構築として実現した点も、このプロジェクトの独創性を際立たせている。
常識的に考えれば絶望的な地域、建物、制度、スケール。そのすべてを、独創的な構想力でストックの限界を乗り越えた本作は、まさに無差別級最優秀賞の名にふさわしい。エンジョイワークスは、初エントリーで初部門最優秀賞という快挙である。
この他にも特筆すべき作品として審査員特別賞を選んでいるが、紙面の都合もあるのでそれらの作品の講評は他の審査員の方々の講評に譲る。
2025年のリノベーション・オブ・ザ・イヤーの審査を通して強く印象付けられたのは、四半世紀の歴史を重ねた日本のリノベーションが、これまでのリノベーションの既成概念を自ら乗り越え、リノベーションをアップデートし続けている状況である。冒頭ではこれを「リノベーションのリノベーション」と呼んだが、そのようなリノベーションの再帰的な振る舞いの核にあるのは、「遊び心」のような基本的態度ではないだろうか。
人口減少と少子高齢化で衰退する地域社会、ストックの劣化と増え続ける空き家、伸び悩む所得に反して高騰する住宅価格、地球規模では気候変動などなど、リノベーションの基本的役割は「住むこと」にかかわる社会課題の解決にある。しかしその解法は、総合グランプリの「人間は、つくることをやめない」が象徴するように、いつだって明るく楽しい。「遊び心」は既存の常識や規範を笑い飛ばして相対化し、まったく未知の領域への挑戦を楽しむ好奇心を持っているからだ。リノベーションの「遊び心」は、自らの常識・セオリーをも疑うことができる。そしてその小さな「遊び心」こそが、リノベーションの未来を私たちの想像よりも少し面白くするのだ。