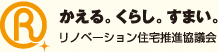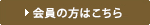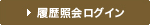受賞作品一覧
講評コメント
選考委員によるコメントをご紹介します。

審査委員長 島原万丈
プロモーション委員長・HOME’S総研所長
1枚の写真が審査員に大きな衝撃を与えた。総合グランプリに輝いた「アーケードハウス」である。ひと気のない薄暗いアーケード商店街にともされた暮らしの灯りが、過去から現在までこの商店街が辿ってきた時間と、これから向かうかもしれない未来を、静かに暖かく照らしていた。
衰退した商店街で空き家になった店舗を、「店」からではなく「住」から再生させるというのは、これまで誰も考えなかったアイデアである。このような灯りが商店街に連なり、すなわち商店街に再び人が住むようになれば、路面の「商」も昔とは違った形に再生するのではないだろうか。LDKの大きなガラス面から見下ろす街の、まだ見ぬ未来の予感にわくわくした。審査会満場一致で決まった総合グランプリである。
「アーケードハウス」を代表として、今年のオブ・ザ・イヤーのノミネート作品は全体的に、社会的な提案性を感じられるものが目立った。これらの作品は、基本的に個人または個社のオーダーに応えてデザインされたものであるが、その視線は物件の背景にある地域社会の課題にまで届いている。それは、何十年もその地にあり続けた既存住宅を活用するからこそ求められる態度というべきもののであろうし、社会から期待されているリノベーションの役割でもあろう。
800万円未満部門最優秀作品の「“高品質低空飛行”に暮らす家〈暮らしかた冒険家 札幌の家〉」と800万円以上部門最優秀作品の「三角屋根のブロック造の家」は、奇しくもどちらも北海道からのエントリーである。いずれも断熱・気密の性能を大幅に向上させ、クライアントの快適性だけにとどまらず、エネルギー問題・地球環境問題に対する既存住宅からの回答となっている。また両作品とも道産材を多用することで、ウッドマイレージCO2の削減とともに地域の経済循環にも目配せがされている。
日本の住宅の弱点は、間違いなく省エネルギー性能だ。2020年に義務化される次世代省エネ基準ですら、外被性能が先進国の水準から大きく立ち遅れていることは、住宅業界の不都合な真実である。断熱・気密に対する認識が低かった時代に建てられた既存住宅はなおのこと、夏は暑く冬は寒い。当然エネルギー消費量は大きい。既存住宅のリノベーションは、そもそも新築行為よりも環境負荷は小さいものの、省エネ性能の低さは既存ストックの泣き所であった。外被性能の向上はコストも知識・技術も要求される改修であるが、中古だからとそこから逃げずに取り組んだ両作品は、リノベーション住宅が進むべき未来をはっきり示したと言える。
無差別級に多数エントリーされたコンバージョン事例は、空き家問題を解決しつつ、インバウンドによる成長戦略や地域活性化に資する、説得力のある提案だったように思う。
激戦の無差別級で、「SPICE MOTEL OKINAWA」(審査員特別賞「インバウンド賞」受賞)、「さらしや長屋」(審査員特別賞「空家活用まちづくり賞」受賞)、「HATCHi金沢」など、いずれもグランプリ級のライバルを押さえて最優秀を勝ち取ったのは、「シーナと一平」だった。街の銭湯をお風呂、飲食店をレストラン、「シーナと一平」をダイニングキッチンとベッドルームと見立てた、街全体がひとつの宿というコンセプトは、リノベーションに不可欠な「見立てる力」を最も象徴的に示した作品である。
さらに、豊島区の椎名町駅という東京都民にもあまり知られていない街の、いかにも古ぼけた、建築物としても特筆すべき取り柄など見当たらない、小さなとんかつ屋の店舗を題材にしたこの作品は、どんな街のどんな建物にも、磨けば光る可能性が潜在していているのだと、全国の街に展開可能な希望を照らした。「シーナと一平」は小さな作品だが、ある意味で大きなリノベーションと言えるかもしれない。
4回目を向かえるリノベーション・オブ・ザ・イヤー2016の総括として、年末恒例の「今年の漢字」にあやかるなら、「灯(あかり/ともしび)」としたい。リノベーションが進むべき未来と、リノベーションによって拓かれる未来の可能性を明るく照らしたコンテストであった。

池本 洋一
SUUMO編集長(株式会社リクルート住まいカンパニー)
最近は第三者視点による客観型記事より、ライターの感情を素直に表現した主観型記事のほうがうける。建物・商品・街の紹介よりも、住人、使った感想、街に暮らす人の話のほうがうける。SUUMOでも街の紹介記事を暮らした経験あるライターやブロガーに「私見」で書いてもらっている。情報の網羅性は従来型の街紹介記事に劣るが、書き手のへの共感が情報量の少なさを上回り「いいね」の数が全然違う。
メディア視点でみると住まい領域では「リノベーション」と「地域活性」系が最も「共感」が獲得しやすい分野だ。なぜか?両者ともに「歴史」があり、「課題」があり、そこに「新規性・意外性」を伴う解決イノベーションがある。それは人の想いや志と経済合理性を交錯させながら生まれている。
昨今のリノベーションオブザイヤーは「デザイン性に優れた空間」では歯が立たない。フォトジェニックであることは1つの競争優位だが、それだけでは賞は取れない。Instagramに代表されるように「フォトジェニック」は既に素人でも創れ、磨かれる時代性となっている。では入賞作品は何が違うのか?
ビジュアル的な魅力はベースとして必要だ。新築風にリフォームしたような作品はその時点で浮かんでこない。だがそれだけでは意外性がない。入賞作品は、その多くが歴史背景、課題、希望、社会との調和、あるいは未来が見える、いずれかのストーリーが描かれている。グランプリや無差別級の最優秀はその点のストーリーがシャープな作品だった。500万円未満部門も単なるカフェ風デザインではなく「シングルの部屋でも人を招く」という希望が秀逸なデザインに落とし込まれているという背景がストーリーにある。
また、今年は断熱などの性能向上に取り組んだものが目を引いた。800万円未満、800万円以上の最優秀がそれだ。自ら勉強し施工もやれることは自分でというセルフ事例も面白いが、らしい空間×性能を両立させた結果、新築同等のコストをかけた事例も評価した。新築より〇割安という価値から抜け出て、新築以上のコストをかける価値があるという許容層がいる。建築許認可、施工スピード欧米と比べ格段に早い日本でこの考え方が主役になることは想像しづらいが、我々メディアは日本のどこかにいるその許容層にその価値を伝え続けていく役割を担っている。日本の未来を見据えた時に持続性ある仕組みとはなにか?真に価値ある住まいとは何か?メディアを主役にしたコンテスト、リノベオブザイヤーはそれを住まい手、事業者に伝えるメッセンジャーである。

圓角 航太
KINFOLK MAGAZINE JAPAN編集長( 株式会社ネコ・パブリッシング)
今回はじめて参加させて頂いた審査会。リノベーション最前線のレベルの高さに激しく驚かされた。住まう人、使う人々の思いや事情が反映されて成立するのがリノベーションの基本と考えるが、今回審査会に並んだ作品はいずれも設計者の「MORE」な提案があったと捉えている。そう、施主の想像を遥かに超える設計者たちの多様な提案。美しい、かっこいいなど見た目だけではない、ネガをプラスに変える機能的なアイデアが高い次元で具現化されており、思わず膝を打たずにはいられない。とにかく日本のリノベーション最前線を思い知らされる実に楽しく有意義な審査会だった。
どの作品も非常に興味深く、甲乙つけがたいものであったが、個人的な趣味も交え、あえてここで特筆させていただきたいのは、「800万円以上_部門別最優秀賞」を獲得したスロウル「三角屋根のブロック造の家」である。本作品の紹介でも記載があるように、北海道の住宅供給公社により1960年代に道内で建設が進められた同地ならではの住宅であるが、いまや築年数の古さや機能性の悪さにより道内でもその数を減らしているのが現状だ。そんな北海道遺産とも言える貴重な建物を見事にリノベーションした本作品。ウッドを基調としたモダンなしつらえは大いに目を楽しませ、また仕切りを取り払い、本来の間取りの悪さも解消している。加えて北海道の厳しい寒さをしのぐべく、様々なパートにおいて抜かりない断熱素材を採用していることも、もちろん評価するべき点だろう。古きものを今のスタンダードで上手に使う好例。ワクワクする作品だった。
さて、来年はどんな作品を見ることができるのだろうか? 日本のリノベーション最前線、いや世界の最前線と形容しても問題ないだろう、そこに追いつけるように、これから1年は私自身も勉強を迫られることになりそうだ。

君島 喜美子
リライフプラス編集担当(株式会社扶桑社)
地域密着、宿泊施設、DIY、コンパクト。
今回、一次審査を通過した作品に多く見られたテーマであり、審査の際にも話題にのぼることが多かった。
そして受賞した作品は、
・既存の良さを生かして建物の寿命を伸ばすこと
・いまそこに暮らす人(もしくは泊まる人)にとってベストな空間にすること
というリノベーションの最大の目的であるこの2つを、気負わず自然に、しかも楽しみながら実現していると感じた。
グランプリを受賞した「アーケードハウス」は、いかにも地方都市にありそうなアーケードに忽然と現れるモダンな空間と、ちょっと寂しい商店街とのギャップにまず惹き付けられる。
賃貸DIY推進賞の「DIY先生がいる工房付、賃貸一棟マンション!」は、まだまだハードルが高いDIYをどう普及させていくか、という課題に対する有効な手段のひとつになっていくのでは、と感じた。
また、特に都市部でニーズの高いコンパクトマンションの事例にも注目したい。コンパクトプランニング賞の「家族4人のシェアハウス」は4人家族で58㎡と決して広いとは言えない空間でありながら4つの個室を確保しつつ、家族が集まるLDKはゆったりと。
図面を見ているだけでも楽しくなるような事例だった。
なんとなくカッコいいから、流行っているから、安くできるからリノベーション、というフェーズから確実に進化して、地に足のついた、骨太なリノベーション事例が増えていると感じた。

坂本 二郎
LiVES編集長(株式会社第一プログレス)
リノベーションオブザイヤー開始当初は、「住まい手の要望をいかに解決したか」といった個々のストーリーを軸に審査していたが、回を重ねるごとに、新しいリノベーションの在り方を示してくれる作品への期待へと審査の基準が変わってきている様に思う。
今回のグランプリは、アーケード内の店舗を住宅に変えた「アーケードハウス」。ビル、倉庫のコンバージョンなどは珍しくなくなったが、密集したアーケードで暮らす、という事例は初めて。シャッター街の空き店舗という課題に対して、リノベーションが取りうる町おこし的な立ち位置を飛び越えて、ストレートに住居とした点が逆にインパクトがあった。
同じく商店街の空き店舗をゲストハウスに変えたという、無差別級を受賞した「シーナと一平」は、飲食店だったという看板や外観を遺しながらのリノベーションで、古くからの住人たちの記憶を繋ぎ止めつつも、外部の来訪者を迎えるコミュニティスポットになっている。
アートアンドクラフトによる「SPICE MOTEL OKINAWA」は、モーテルの再生。他にも、受賞は無かったが、空家をインバウンド向けの民泊施設にリノベーションした作品もあった。空家、空き店舗や施設は今や地方だけの問題ではなくなってきている。
「アーケードハウス」は特に柔軟な住まい手の存在があって実現したものとも思うが、こうした住宅、もしくは他の用途への活用事例が全国的に増えることに期待したい。また、建物の佇まいはそのままに、新たな価値を付加した「シーナと一平」や、「SPICE MOTEL OKINAWA」では、何を引き継ぎ、何を残すかのジャッジに、他のものづくりとは違った〝目利き〟のセンスがいかに重要であるかを改めて感じた。現在はリノベーションによるゲストハウスやシェアハウスが数多くつくられているが、これらから得た空間の発想が「家族4人のシェアハウス」のように、一般住宅の空間に活かされている点も興味深かった。
住宅、店舗、オフィス、宿泊施設、オフィ商店街。リノベーションのテリトリーは日々広がり続けており、それらの経験が垣根を越えて融合し合い、再び住宅へとフィードバックされて、新しい住まい方の常識を生み出している。今後もこのコンテストでは、「アーケードハウス」のような〝想定外〟の暮らし方を見せ続けて欲しいと思う。

徳島 久輝
RoomClip mag 編集長(Tunnel株式会社)
リノベーション・オブ・ザ・イヤーも今年で4回目を迎えたが、社会の中で「リノベーション」が果たす役割が、ますます大きくなってきていることを感じる。昨年度のグランプリ「ホシノタニ団地」(株式会社ブルースタジオ)が2016年度グッドデザイン大賞候補6作品に残ったことは象徴的な出来事だった。
本年度のグランプリを獲ったのは「アーケードハウス」(株式会社タムタムデザイン)。商店街のアーケード2階に存在するとは思えない「モダン」な住まい。アーケードの外から見るとまるでカフェのようであるが、実際には人が住んでいるという驚き。住まいとしても外壁からの採光が望めないことからインナーバルコニーを作るなど、リノベーションの醍醐味である「ネガティブな要素をポジティブに変換する工夫」も随所に盛り込まれている。
活気がなくなり、空き店舗だらけのアーケード街は多数存在している。もしこのような暖かい光に包まれた家が、そんなアーケード街にびっしり埋まるようなことがあれば、街づくりの新しいヒントになるかもしれない。そして1階に素敵なお店ができるようなことがあれば等々、色々な妄想が膨らむところが個人的には特に好きだった。
もちろん、社会的な文脈はなくとも、個人邸で目一杯「ワガママ」に施主のスタイルを貫かせてあげられることはリノベーションの大きな役割だと思う。わかりやすくファンがつきそうな「カフェ部屋ライフ」(REISM株式会社)がある一方で、モルタルマニア(株式会社ニューユニークス)なんていう「ニッチ」なものまで。
RoomClipで発表している「RoomClip Award 2016」でもそうであったが、年を追うごとに新しい「スタイル」は生まれている。見た目のスタイルの数が増えれば増えるほど、人々が自分自身の好きなもの・ことをみつけられていて、それを設計・施工がきちんと汲み取り、具現化してあげられているということ。来年以降もたくさんの「ワガママ」スタイルが見られることを心待ちにしている。

八久保 誠子
HOME'S PRESS 編集長(株式会社ネクスト)
昨年のリノベーション・オブ・ザ・イヤーは、あらゆる文脈での「再生」が、内と外に感じられた事例が多数見られた。
その中で株式会社ブルースタジオの「ホシノタニ団地」がグランプリを受賞。
そのリノベーションの可能性の大きさを証明した事例は「2016年度グッドデザイン金賞」にも輝き、その他のエントリー事例を含めてリノベーションという手法の拡がりと深みを感じた。
そして今年のリノベーション・オブ・ザ・イヤー2016。
さらにエントリー事例は、拡がりをもち、多様性を含み「賞を選ぶ」という過程で大いに審査員を悩ませた。
たとえば同じ施工価格帯のリノベーションであっても「これは同じように比較してよいのだろうか?」と思うほど課題設定も、アプローチも、そしてリノベーションによって生み出された成果も違うのだ。
それでも、個人的に今年らしさをあえていうとするならば、「より洗練し、より機能させたリノベーション」であろうか。
デザインはより機能的に洗練され(カフェ部屋ライフ・モルタルマニア)、住居としての機能も向上し(暮らしかた冒険家 札幌の家・家族4人のシェアハウス)、古いビルを新たに宿泊施設と街や旅の拠点として機能させる事例(HATCHi金沢・SPICE MOTEL OKINAWA)も登場した。
みごとグランプリを受賞したのは、株式会社タムタムデザインの「アーケードハウス」。
商店街の2階を住居として用途変更することで空き店舗に需要を生み出す例だが、審査員の心を捉えたのは暗いシャッターの閉まった商店街に、明るい住まいが“ぽっと出現した”その写真であった。
画家エドワード・ホッパーの「ナイトホークス」のようなインパクトがありながら、どこかやはり住宅の暖かさが感じられるこのリノベーションは、住まいの灯りがあらためて「街の灯り」であることを気づかせてくれる。
たくさんの「豊かな暮らし」と「街の灯り」を創り出していけることにリノベーションのプレイヤーたちが気づいたことを感じさせてもらえた「リノベーション・オブ・ザ・イヤー2016」であった。

濱口 重乃
エル・デコ編集長(株式会社ハースト婦人画報社)
インテリア&デザインの潮流を発信するインターナショナル誌「エル・デコ」の編集者として、今回はじめてリノベーション・オブ・ザ・イヤーの最終選考会に参加させていただいたが、日本的なリノベーションの幅広さや奥深さに驚いた、というのが率直な感想だ。
選考会場に並んだ候補作の数々は、作り手と住み手の想いを濃厚に宿しているようで、当然ながらどれも個性的だった。狭小や変形や経年といった建物のデメリットを克服したり、家族構成の変化に軽妙な空間構成で対応したり、施主のライフスタイル嗜好を徹底的に追求したり……。住み手の夢を具現化するための、あるいは問題を解決するための、発想力豊かなリノベーションは、海外で目にする事例ともまた違う、まさに“日本的”と呼べるキメ細やかなものだった。
冒頭に吐露した如く、その多彩ぶりに一目圧倒された身としては、表層というか形而下だけに着目すると、目移りしてイケない。ここは敢えて、リノベーションのテクニカルな分析・評価は他の選考委員に(勝手に)委ねるとして、デザイン界で昨今囁かれている“デザインのこれから”という文脈に沿って選考させてもらった。
「これからのデザインとは?」を問うたとき、デザインの世界では、「サステイナブルな社会を作ってゆくためにいかに貢献できるか」というエシカルな側面に価値基準が移行しつつある。そのデザインは、それぞれの社会が抱える問題を解決できるのか、人と人とのコミュニケーションを豊かに醸成させることができるのか? もはやデザインには、ものの形や色を追求するだけでなく、ソリューションとしての力が求められている。それに比例するように、デザインの領域は、目に見えない部分、つまり映像には写らない深いところにまで広がってきているようだ。
といった視点で作品群を眺めると、鮮やかに目を惹いたのが、そのリノベーションによって何を解決したいのか、という明確な理念を掲げた作品だった。もっといえば、住み手という“個”に対するソリューションにとどまることなく、地域コミュニティの再生だったり、古き善き住宅建築の継承だったり、自然との共生だったり、社会に向かって大きく開かれたそもそものコンセプトだった。
総合グランプリに輝いた「アーケードハウス」、無差別級部門での受賞となったカフェ&お宿「シーナと一平」はその筆頭に思えた。いずれも昭和の懐かしい商店建築だが、前者はアーケード商店街の空き店舗をモダンで美しい住居に、後者はとんかつ店だった木造建築を最大限に活かして情緒豊かなカフェ&宿にトランスフォームしてみせた。
大資本の席巻と消費形態の変容もあって、個人商店が次々と商いを閉じシャッター街が急増するなか、人や土地の記憶を宿した建築をいかに継ぎ、地域を再生してゆくかは、日本の町々が抱える大きな問題といえる。ふたつの作品とも建物前面に大きな開口部を設けていたが、そこから漏れ見える温かな灯りや屋内の朗らかな景色は、日本的リノベーションの未来を明るく物語るようだった。
ほかでは、北海道の「“高品質低空飛行”に暮らす家<暮らしかた冒険家 札幌の家>」、滋賀の「DIY先生がいる工房付、賃貸一棟マンション!」、京都の空家活用×まちづくりリノベ「さらしや長屋」、沖縄の開放感あふれるデザインモーテル「SPICE MOTEL(OKINAWA)」など、地方都市のリノベーション物件に印象的なものが多かった。これも今の時代の空気なのかもしれない。

宮沢 洋
日経アーキテクチュア編集長(株式会社日経BP 社)
今回、初めて審査に参加させていただいた。「日経アーキテクチュア」は建築専門家向けのメディアで、「日経」という冠の通り、建築を「経済」や「社会」の視点から取り上げることに特色がある。そのため、住宅であっても、それが「社会に対してどんな意味や影響力を持つか」を常に考えてしまう癖がついている。
実は、雑誌に載せる住宅を選ぶときには、「デザインはいいけれど社会性がね…」と、大半がボツになってしまう。だが、今回の最終選考に残った候補作は全く違った。
総合グランプリの「アーケードハウス」は「デザイン性+社会性」の両方を備えた最たる事例だろう。往時の勢いを失ったアーケード街の店舗を、大開口を生かしたままリビングに変えてしまうというインパクト。この事例が多くのシャッター商店街に何らかのヒント、あるいは勇気を与えるであろうことは間違いない。
個人的に強く引かれたのは、「空家活用まちづくり賞」を受賞した「さらしや長屋」だ。大正時代に建てられた長屋のリノベーション。幅1.5mほどのトンネル路地の奥に並ぶ4軒長家を、路地ごと改修した。一般の方は「建て替えればいいのではないか」と思われるかもしないが、接道条件を考えると、この敷地内で建て替えるのは困難だ。何もしなければ、空き家のまま周囲との一体開発を待つことになる。ならば細い共用路地を魅力に変え、子どものいる入居者を募ろうという逆転の発想、そしてそれを本当にやり遂げてしまった実行力に敬服する。
今回の審査を通してリノベーションが「感度の高い一部の人たちの特殊解」から「一般解」へと変わりつつあることを感じ、専門誌をつくる立場としても勇気付けられた。