受賞作品一覧
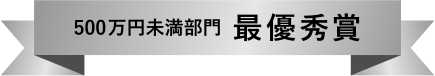
株式会社水雅
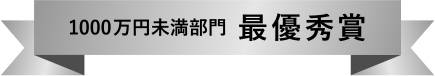
株式会社ブルースタジオ

株式会社grooveagent

株式会社ブルースタジオ

株式会社リビタ
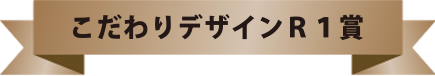
株式会社ニューユニークス

株式会社タムタムデザイン
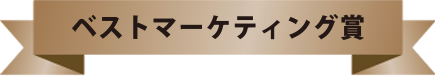
株式会社フージャースコーポレーション

イーコンセプト株式会社

株式会社連空間デザイン研究所
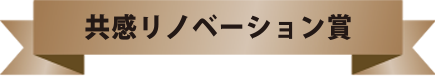
内村建設株式会社
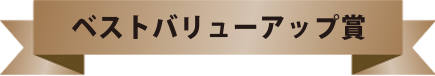
株式会社八清
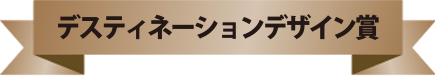
株式会社タムタムデザイン
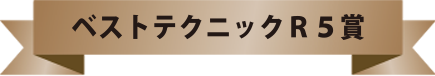
株式会社リビタ

有限会社熊本建設

株式会社アトリエいろは一級建築士事務所

株式会社アートアンドクラフト









