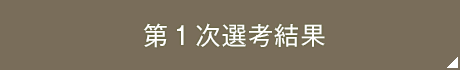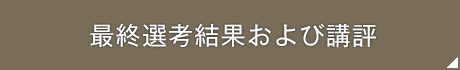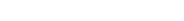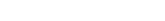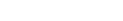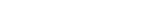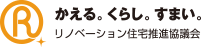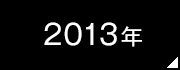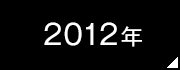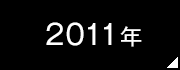燃えやすい木造密集地域を防災のために建て替えるのではない。木密に萌えてしまう僕たちは、木密をリノベーションして、かつ防災性を高めたい。それが今年のテーマである。
『それでも木密に住みたい!』という本もあるほど、木密地域には魅力がある。密集しているからこそ、路地があり、人と人がふれあいやすく、味わいがあり、界隈性がある。だから人は、木密に萌えるのだ。
しかし、たしかにそこは地震や火事の際の危険は大きい。あっという間に火の海になり、すごい熱風で火の粉が舞って、木密地域以外にまで火災を広げる危険がある。だから、2020年の東京オリンピックに向けて、木密地域はまさに標的にされている。どんどんぶっ壊してビルにしようとされている。
東京に限らない。今まで何十年もの間、日本中で、密集した住宅地、商店街、歓楽街、飲み屋街、ヤミ市などなどが壊され、衰退し、その代わりにツルツルピカピカのビルに建て替えられた。たしかにそれで街がきれいになったり、マンションができて人口が増えたり、おしゃれな店ができたりもした。しかし、それで必ずしも街が生き生きとよみがえったとは限らないような気がする。たとえばハモニカ横丁のない吉祥寺なんて想像できないように、木密だからこそ、街の魅力を倍加している例はいくらでもある。
また、阪神淡路大震災の時、焼け野原になった木密地域にマンションを建てて住民を戻したら、以前の住民コミュニティが失われ、孤独にさいなまれて自殺する人すらたくさんいたことは周知の事実である。
さらに、これからの人口減少社会の中で、ビルに建て替えても、そこに入る人も店もオフィスも足りなかったりする。防災性を高めることと、2階建ての木造家屋を10階建てのビルにすることは、かつては同じで良かったが、これからは違うはずだ。
ただ燃えやすいというだけの理由で、どんどん壊して、ただ広場にするとか、道路を拡幅するとか、ビルにするとかでは脳がなさ過ぎる。だから、住宅や商店それ自体をリノベーションするだけでなく、木密地域全体を、街路なども含めて、街全体としてリノベーションすることで、建物を燃えにくくし、防災性を高め、かつコミュニティを維持する、もしかしてもっとコミュニティを強化する、そしてコミュニティを強化することで防災性も高まる、「萌えつつ燃えない防災」「燃えないが萌える防災」、それが課題だ。
審査委員長 三浦 展